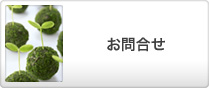トップページ > 新着情報
「マイナンバーカードを健康保険証に」、「被扶養者に国内居住要件」などを盛り込んだ健保法等の改正 官報に公布 (2019年5月23日)
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる規定を設けることや、被扶養者の要件に国内居住要件を加えるなどの改正を盛り込んだ「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」が、令和元(2019)年5月15日、参議院本会議で可決、成立したことはお伝えしましたが、その改正法が官報に公布されました(令和元年5月22日公布)。
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる規定の導入(オンライン資格確認の導入)は、公布日から2年を超えない範囲内で政令で定める日からの施行、被用者保険の被扶養者等の要件に、原則として国内に居住していること等を追加する改正は、令和2(2020)年4月1日からの施行とされています。
ひとまず、官報の内容と、改正法案の概要をご確認ください。
<医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20190522/20190522g00015/20190522g000150005f.html
※上記の官報情報は、直近30日分については無料で閲覧できます(それ以後は閲覧不可〔有料となります〕)。
〔参考〕医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案の概要
https://www.mhlw.go.jp/content/198-01.pdf
平成30年度の有効求人倍率は1.62倍 過去2番目の高水準 (2019年5月7日)
厚生労働省から、「一般職業紹介状況(平成31年3月分及び平成30年度分)」が公表されました(平成31(2019)年4月26日公表)。
平成30(2018)年度平均の有効求人倍率については、前年度より0.08ポイント上昇し1.62倍でした。
上昇は9年連続で、過去2番目の高水準となっています。
人手不足を背景に、企業の求人意欲が強い状況が続いているようです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<一般職業紹介状況(平成31年3月分及び平成30年度分)について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000192005_00002.html
賃金等請求権の消滅時効の在り方 論点整理が続く (2019年5月7日)
厚生労働省から、平成31(2019)年4月25日に開催された「第8回賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」の資料が公表されました。
労働基準法第115条における賃金等請求権の消滅時効の期間は2年とされていますが、平成32年(2020年)4月から、民法の一部改正により、賃金を含む一般債権の消滅時効の期間について、複数あ った時効の期間が統一され、「知った時から5年(権利を行使することができる時から10年の間に限ります)」とされることになりました。
これに伴い、労働基準法に規定する賃金等請求権の消滅時効の期間をどうするか?ということで行われているのが、この検討会での議論です。
今回は、賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する論点の整理が進められました。
しかし、未だに「改正民法と労働基準法を可能な限り併せる考え方と、賃金等請求権の特殊性を踏まえ、民法と労働基準法とは別個のものとして整理する考え方があるが、どう考えるか。」という 根本的な部分についても、方向性が明確には定まっていないようです。
改正民法の施行まで1年を切りました。
企業に大きな影響を与える論点ですから、労働政策審議会での本格的な議論によって、その方向性が明確になるのが待たれます。
不合理な待遇差解消のための点検等 業界別マニュアルを公表 (2019年4月8日)
厚生労働省から、「不合理な待遇差解消のための点検・検討 マニュアル(業界別マニュアル)」が公表されています。
「働き方改革関連法」により、2020年4月から、正社員とパートタイム・有期雇用・派遣労働者との間の不合理な待遇差が禁止されることとなります(中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法の適用は1年遅れ)。
このマニュアルは、法改正に備えて、パートタイム・有期雇用労働者等の数又は割合が高い業界(スーパーマーケット業、食品製造業、印刷業、自動車部品製造業、生活衛生業、福祉業、労働者派遣業)について、企業が円滑に取組を進めることができるように作成されたものです。
また、上記7業界に加え、「業界共通編」も作成されています。
このマニュアルにおいては、「働き方改革関連法」に沿って不合理な待遇差を解消し、雇用形態に関わらない公正な待遇を実現するための考え方と具体的な点検・検討手順が詳細に解説されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<不合理な待遇差解消のための点検・検討 マニュアル(業界別マニュアル)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03984.html
在職老齢年金の計算の基準となる額の改定などについてお知らせ(日本年金機構) (2019年4月8日)
日本年金機構から、平成31(2019)年4月分からの「年金額」および「在職老齢年金の支給停止基準額(支給停止調整変更額・支給停止調整額)」について、お知らせがされています。
平成31年4月分(6月14日支払分)からの年金額は、法律の規定により、前年度から0.1%の増額となります。
また、平成31年度の在職老齢年金に関して、60歳台前半(60歳〜64歳)の支給停止調整変更額と、60歳台後半(65歳〜69歳)と70歳以降の支給停止調整額が、法律に基づき、46万円から「47万円」に改定されます。なお、60歳台前半の支給停止調整開始額(28万円)については変更ありません。
在職老齢年金の支給停止調整変更額・支給停止調整額の改定については、老齢厚生年金を受給しながら働いている従業員の年金額に影響する可能性があります。
年金額が変わったのはなぜ?」といった質問があるかもしれませんので、今一度確認しておきましょう。
しかし、1万円上げたところで・・・とか思いますがねぇ。