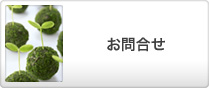トップページ > 新着情報
短時間労働者へのさらなる社会保険の適用拡大 検討を開始 (2018年12月20日)
厚生労働者から、平成30年12月18日に開催された「第1回 働き方の多様化を踏まえた社会保険の対応に関する懇談会」の資料が公表されました。
今回が初会合であるこの懇談会の趣旨は次のとおりです。
⇒
法律上、短時間労働者に対する社会保険(厚生年金保険・健康保険)の適用範囲については、平成31(2019)年9月末までに検討を行うこととされている。
加えて、平均寿命が延伸し「人生100年時代」を迎え、「教育・仕事・引退」という3ステージの単線型の人生からマルチステージの人生を送るようになる中で、複線型の働き方など働き方の多様化に向けた動きが生じている。
これらの動きを踏まえた社会保険制度としての課題や対応について、社会保障審議会の医療保険部会や年金部会における検討に資するよう、保険局長及び年金局長の招集により、関連分野の有識者や労働者・使用者団体からなる懇談会を開催する。
--
そして、この懇談会における検討事項は、次のとおりです。
・短時間労働者に対する社会保険の適用範囲のあり方
・働き方の多様化等を踏まえた社会保険の適用におけるその他の課題
特に注目を集めているのは、「短時間労働者に対する社会保険の適用範囲」です。
これまでに、次のように適用拡大が進められてきました。
①2016年10月~
501人以上の企業で、月収8.8万円以上等の要件を満たす短時間労 働者に適用拡大。
②2017年4月~
500人以下の企業で、労使の合意に基づき、企業単位で、短時間 労働者への適用拡大を可能とする。(国・地方公共団体は、規模 にかかわらず適用とする)
ここからさらに適用拡大を進めようというのが今後の検討課題です。具体的には、「2020年9月まで」に、更なる適用拡大について検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を実施することとしています。
パートさんたちに大きな影響を与えるこの改正案。今後の動向に注目しましょう。
医師の働き方改革で上限超えの場合インターバル9時間提言も現場からは「厳しい」の声が (2018年12月20日)
厚生労働省から、平成30年12月17日に開催された「第14回医師の働き方改革に関する検討会」の資料が公表されました。
医師の時間外労働規制のあり方については、追加的健康確保措置の検討が行われています。
簡単いうと、医師を、一般的な医療機関の医師、地域医療に従事する医師、専門性や技能などを高めたい若手医師の3パターンに分類し、地域医療や、技能を高めたい若手医師は過酷な医療現場で長時間労働が想定されることから、勤務間インターバルや連続勤務時間の制限を義務付けるといった案を示しています。
勤務間インターバルの時間(休息時間)については、医師の健康を維持するには9時間が必要と判断。宿直明けは2日分に当たる18時間、宿直も含めた連続勤務時間は28時間といった案となっています。
しかし、複数の委員から「かなり厳しい設定」、「義務化したら現場はとても回らない」などといった批判が相次いだようです。
厚生労働省では、時間外労働の上限も含めて、年内にはまとめる方針とのことですが、どのように、現場からの意見との調整を図っていくのか、動向に注目です。
国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除制度 事務の取扱いについて通達 (2018年12月10日)
厚生労働省から、「国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除制度の施行に伴う事務の取扱いについて(平成30年12月6日年管管発1206第1号・2号)」という通達(通知)が発出されました。
以前からお伝えしていますが、平成31年4月1日から、国民年金の第1号被保険者の保険料の産前産後期間の免除制度が施行されます。
この通達では、日本年金機構などにおける事務の取扱いについて、制度の内容とともに詳細が定められています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除制度の施行に伴う事務の取扱いについて(平成30年12月6日年管管発1206第1号・2号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T181207T0010.pdf
非正規と正規の基本給の格差は不合理(高裁で判決) (2018年12月10日)
「産業医科大病院の事務として働いている臨時職員の女性が、正規職員と給与に差があるのは労働契約法違反だとして、大学側に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、高等裁判所が「待遇の差は不合理で違法」と判断し、請求を退けた地方裁判所の判決を取り消し、大学側に約113万円の支払いを命じた。」といった報道がありました(判決は平成30年11月29日)。
裁判長は「女性は30年以上勤務し、業務に習熟しているのに、同時期に採用された正規職員の基本給との間に約2倍の格差が生じている」と指摘。
労働契約法の改正によって、非正規労働者との不合理な労働条件が禁じられた平成25年4月以降、月額3万円を支払うように命じたとのことです。
この訴訟で、訴えの根拠となっているは、労働契約法第20条です。本当に、同条をめぐる訴訟が新聞などに取り上げられる機会が増えています。今後の判例に注目です。
賃上げを行った企業は89.7% 前年を1.9p上回り過去最高を更新(厚労省の賃上げ調査) (2018年11月30日)
厚生労働省から、「平成30年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況」が公表されました(平成30年11月27日公表)。
「賃金引上げ等の実態に関する調査」は、全国の民間企業における賃金の改定額、改定率、改定方法などを明らかにすることを目的に、毎年8月に実施されるものです。
「製造業」及び「卸売業,小売業」については常用労働者30人以上、その他の産業については常用労働者100人以上を雇用する企業から抽出して調査を行い、平成30年は、有効回答を得た企業のうち、常用労働者100人以上の1,578 社について集計したものです。
調査結果(2018(平成30)年における状況)のポイントは次のとおりです。
●賃金の改定
・「1人平均賃金を引き上げた・引き上げる」企業割合は89.7%(前年87.8%)で、前年より上昇(比較可能な1999年以降で最高)。
・1人平均賃金の改定額(予定を含む。)は5,675円(前年5,627円)で、前年より増加(これも比較可能な1999年以降で最高)。改定率は2.0%で、前年と同水準。
●定期昇給等の実施
・賃金改定が未定以外の企業(賃金の改定を実施し又は予定している企業及び賃金の改定を実施しない企業)のうち、定期昇給を「行った・行う」企業割合は、管理職69.7%(前年69.0%)、一般職80.1%(同 77.5%)で、管理職、一般職ともに前年より上昇。
・定期昇給制度がある企業のうち、ベースアップを「行った・行う」企業割合は、管理職24.2%(前年22.9%)、一般職29.8%(同 26.8%)で、管理職、一般職ともに前年より上昇。統計上は、順調に賃上げが進んでいるようです。
厚生労働省では、企業の業績が向上していることや労働力を確保したい狙いが背景にあると分析しているようです。