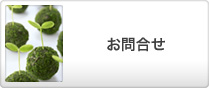トップページ > 新着情報
同一労働同一賃金に関する新たなリーフレットを公表(厚労省) (2019年2月1日)
厚生労働省から、リーフレット 「パートタイム・有期雇用労働法が施行されます」などが公表されました。
「パートタイム・有期雇用労働法」は、現行のパートタイム労働法の名称を改めたものです。
働き方改革関連法による法改正によって、パートタイム労働法の対象に有期雇用労働者も含めることとし、そのような名称に変更されることになりました。
これは、同一労働同一賃金の実現に向けた法改正の一環であり、その施行は、 2020(平成32)年4月1日(中小企業では1年遅れの適用)とされています。
この法改正に対応するための自社の制度の整備には、時間を要することが予想されます。
これらのリーフレットなども参考にして、準備を進めるようにしましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<リーフレット 「パートタイム・有期雇用労働法が施行されます」>
https://www.mhlw.go.jp/content/000471837.pdf
<パンフレット「平成30年度労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>>
https://www.mhlw.go.jp/content/000473039.pdf
<リーフレット「雇用形態に関わらない公正な待遇の確保」【省令・指針反映版】>
https://www.mhlw.go.jp/content/000474490.pdf
学校における働き方改革推進本部を設置(文科省) (2019年2月1日)
文部科学省から、「学校における働き方改革推進本部」に関する資料などが公表されました(2019(平成31)年1月30日公表)
同年1月25日、中央教育審議会において、「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について」の答申がなされたことはお伝えしました。
これを受けて、学校における働き方改革を推進し、その実効性を高めるために設置されたのが「学校における働き方改革推進本部」です(本部長は文部科学大臣)。
設置に当たり、文部科学大臣は、答申を踏まえて働き方改革を強力に進める旨のメッセージを発出しています。
今後は、この推進本部の下で、文部科学省が学校と社会の連携の起点・つなぎ役としての役割を前面に立って果たし、学校における働き方改革を推進していくとのことです。
平成31年度の年金額は0.1%引上げ 在職老齢年金の計算で用いる額も改定 (2019年1月18日)
国民年金制度・厚生年金保険制度による年金額について、厚生労働省から次のようなお知らせがありました(2019(平成31)年1月18日公表)。
●2019(平成31)年度の年金額は、年金額改定に用いる物価変動率(1.0%)が名目手取り賃金変動率(0.6%)よりも高いため、新規裁定年金・既裁定年金ともに、名目手取り賃金変動率(0.6%)を用います。さらに平成31 年度は、名目手取り賃金変動率(0.6%)にマクロ経済スライドによる平成31 年度のスライド調整率(▲0.2%)と平成30 年度に繰り越されたマクロ経済スライドの未調整分(▲0.3%)が乗じられることになり、改定率は0.1%となります。
このように、2019(平成31)年度の公的年金の支給額は、前年度の額から0.1%引き上げられることが決まりました。
今回の改定においては、4年ぶりにマクロ経済スライドが発動され、加えて、未調整分の繰越(キャリーオーバー)も発動されました。そのため、物価や賃金の上昇より、年金額の引き上げ幅は低くなっており、実質的な価値は目減した形になります。
その他、厚生年金保険制度における在職老齢年金の支給停止額の計算に用いる支給停止調整額・支給停止調整変更額が、46万円から「47万円」に改定されることが公表されています。
〈補足〉支給停止調整開始額28万円は改定なし。
また、国民年金制度の平成31年度・平成30年度の保険料額も公表されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<平成31年度の年金額改定について>
https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/000468259.pdf
就業者が2040年に1285万人減少の可能性 女性や高齢者の参加が重要(厚労省) (2019年1月18日)
厚生労働省から、「平成30年度第8回雇用政策研究会」の資料が公表されました(2019(平成31)年1月15日公表)。
その中で、「雇用政策研究会報告書(案)」が提示されています。
これによると、2040年まで経済がゼロ成長で推移し、女性や高齢者の労働参加が進まない場合には、2040年の就業者数は2017年に比べ1285万人減少し、5245万人に落ち込むと試算しています。
減少幅は働き盛りの30〜59歳で大きく、成長に向けた大きな阻害要因になるとみています。
これに対し、経済が成長し、女性や高齢者の就業が進んだ場合には、2040年に就業者を6024万人は確保できると試算。
人口減で就業者数が長期的にマイナスに陥る事態は避けられない模様ですが、人工知能(AI)などの活用により生産性は向上し、一定の成長を実現できると見込んでいるようです。
同報告書(案)では、2040年の我が国が目指すべき姿として、「一人ひとりの豊かで健康的な職業人生の実現、人口減少下での我が国の経済の維持・発展」を掲げています。
その実現のためにも、女性や高齢者の労働参加を進める政策が積極的に実施されることになりそうです。
協会けんぽが平成31年度の収支見込みを公表_介護保険料率は引上げの見込み (2019年1月7日)
全国健康保険協会(協会けんぽ)から、「平成31年度政府予算案を踏まえた収支見込について(概要)」が公表されました(平成30年12月26日公表)。
●医療分については・・・
平成31(2019)年度協会けんぽの収支見込みについては、平均保険料率を10%と設定した上で、政府予算案(消費税の引き上げや薬価の実勢価格の反映に伴う診療報酬改定等)を踏まえて算出した結果、単年度収支差は5,200億円、平成31年度末時点の準備金残高は3兆3,200億円が見込まれるとのことです。
「平均保険料率10%」を前提した内容となっていますので、平成31(2019)年度の協会けんぽにおける都道府県単位保険料率については、大幅な変更はないかもしれません。
●介護分については・・・
介護保険の保険料率については、単年度で収支が均衡するよう、介護納付金の額を総報酬額で除したものを基準として算出することになりますが、平成31(2019)年度の介護納付金の金額等を踏まえると、平成31(2019)年度の介護保険料率は、平成30年度の1.57%よりも0.16%ポイント上昇し、「1.73%」になるとのことです。
まだ、確定したわけではありませんが、平成31(2019)年度の協会けんぽにおける介護保険料率(全国一律)については、そのように引き上げられることになりそうです。